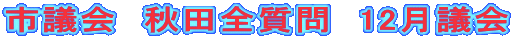
����������i�N���b�N����Ƃ����܂ŃW�����v���܂��j
�E���{��̋������n�邱�Ƃɂ���
�E�w�щ��P�v���W�F�N�g���i���Ƃɂ���
�E�w�K�x�����ɂ���
�E����n��̈�ِ����ɂ���
�E�X�H����LED���E�h�Ƒ�ɂ���
�E����w�O���ւ̃z�e���U�v�ɂ���
 �`���{��̋������n�邱�Ƃɂ��ā`
�`���{��̋������n�邱�Ƃɂ��ā`
 �s���́u���{��̋�����v��n��Ƃ����u�헪�v��\�����邽�߂ɂ́A�����̗\�Z�ƘJ�͂��K�v�����A�X�̐�p���ǂ̂悤�ɕ\�����Ă����̂��f���܂��B
�s���́u���{��̋�����v��n��Ƃ����u�헪�v��\�����邽�߂ɂ́A�����̗\�Z�ƘJ�͂��K�v�����A�X�̐�p���ǂ̂悤�ɕ\�����Ă����̂��f���܂��B
 �u���{��̋�����v�ɂ��ẮA�w�Z�Ɖƒ�ƒn�悪���ꂼ��̐ӔC���ʂ������ŁA�e�⋳�t��n��̑�l�������A�т��A���M�������A�������̒��ɂ��������������āA�`����ׂ����Ƃ�`���A�u������p���E�`���v���Ă����B�����āA�q�ǂ����s�̕�Ƃ��Ĉ�ĂĂ����B���̂悤�Ȏ��������āu���{��̋�����v�Ƃ��ĂƂ炦�Ă���Ƃ��łɂ����������Ƃ���ł��B������������邽�߁A�w�Z�ւ̐l�I�x����n��̋���͂̊��p�Ȃǂ��l���Ă���܂��B�K�v�ȗ\�Z���A��̓I�ȕ���ɂ��ẮA�W�����Ƙb�������Ȃ���i�߂Ă��������Ǝv���܂��B
�u���{��̋�����v�ɂ��ẮA�w�Z�Ɖƒ�ƒn�悪���ꂼ��̐ӔC���ʂ������ŁA�e�⋳�t��n��̑�l�������A�т��A���M�������A�������̒��ɂ��������������āA�`����ׂ����Ƃ�`���A�u������p���E�`���v���Ă����B�����āA�q�ǂ����s�̕�Ƃ��Ĉ�ĂĂ����B���̂悤�Ȏ��������āu���{��̋�����v�Ƃ��ĂƂ炦�Ă���Ƃ��łɂ����������Ƃ���ł��B������������邽�߁A�w�Z�ւ̐l�I�x����n��̋���͂̊��p�Ȃǂ��l���Ă���܂��B�K�v�ȗ\�Z���A��̓I�ȕ���ɂ��ẮA�W�����Ƙb�������Ȃ���i�߂Ă��������Ǝv���܂��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 �`�w�щ��P�v���W�F�N�g�ɂ��ā`
�`�w�щ��P�v���W�F�N�g�ɂ��ā`
���Ɂu�������k�̊w�͌���v�̎��_����A�u�w�щ��P�v���W�F�N�g���i���Ɓv�ɂ��Ă��q�˂������܂�
����ł͊w�Z���璷�Ɋm�F���܂߁A���_���f���܂��B
 ����ψ���ł́u����s�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���v����A�u�w�͌���Ɍ�����3�̒Ǝ��g�݁v���A���݁A���̎��g�݂��s���Ă���Ǝv���܂����u�ψ���̍\���v�y�сu�R�̒Ǝ��g�݁v�ɂ��Ă��������������B
����ψ���ł́u����s�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���v����A�u�w�͌���Ɍ�����3�̒Ǝ��g�݁v���A���݁A���̎��g�݂��s���Ă���Ǝv���܂����u�ψ���̍\���v�y�сu�R�̒Ǝ��g�݁v�ɂ��Ă��������������B
 �w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���́A����Ɋւ���w���o���҂�s�������w�Z�̍Z���APTA��A�n��A�s���S���ۂ̑�\���ψ��Ƃ���15���ō\������Ă���܂��B�w�Z�A�ƒ�A�n��Ɍ������u3�̒v�̓��e�ɂ��܂��ẮA�w�Z�����āA���Ƃ̒��Łu�l���A�܂Ƃ߁A���\����v���ݒ肵�A�u1���Ԃ̊w�K�ڕW�̒v��u�l���������o������̍H�v�v�Ɏ��g�ނ��Ƃ���Ă��܂��B�ƒ�ւ́A�����K�����������A�u�m�[���f�B�A�E�`�������W�v��u���Q�E���N���E�����͂�v�Ɏ��g�ނ��ƁA�n��ւ́u�������v����u�n��s���ւ̎Q���v�֊������L����悤���g��ł������Ƃ���Ă���܂��B
�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���́A����Ɋւ���w���o���҂�s�������w�Z�̍Z���APTA��A�n��A�s���S���ۂ̑�\���ψ��Ƃ���15���ō\������Ă���܂��B�w�Z�A�ƒ�A�n��Ɍ������u3�̒v�̓��e�ɂ��܂��ẮA�w�Z�����āA���Ƃ̒��Łu�l���A�܂Ƃ߁A���\����v���ݒ肵�A�u1���Ԃ̊w�K�ڕW�̒v��u�l���������o������̍H�v�v�Ɏ��g�ނ��Ƃ���Ă��܂��B�ƒ�ւ́A�����K�����������A�u�m�[���f�B�A�E�`�������W�v��u���Q�E���N���E�����͂�v�Ɏ��g�ނ��ƁA�n��ւ́u�������v����u�n��s���ւ̎Q���v�֊������L����悤���g��ł������Ƃ���Ă���܂��B
 ����ł́A�w�Z�ɑ���Ǝ��g�݂ɂ��Ďf���܂����A�V�w�K�w���v�j�̎��{���ɂ��A���̒���g�݂ɕύX����P��������A�܂��́A�������̂ł��傤���B
����ł́A�w�Z�ɑ���Ǝ��g�݂ɂ��Ďf���܂����A�V�w�K�w���v�j�̎��{���ɂ��A���̒���g�݂ɕύX����P��������A�܂��́A�������̂ł��傤���B
 �w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���ł܂Ƃ߂�ꂽ3�̒́A�V�w�K�w���v�j���ŋ��߂��Ă���܂��Ƃ���ɍ��v�������܂��̂ŕύX���͍s���Ă���܂���B
�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���ł܂Ƃ߂�ꂽ3�̒́A�V�w�K�w���v�j���ŋ��߂��Ă���܂��Ƃ���ɍ��v�������܂��̂ŕύX���͍s���Ă���܂���B
 ����ł́A���ɁA�ƒ�ł̎��g�݂ł����A����22�N�x�̎��тȂǂ��܂Ƃ܂��Ă���A���̏���тȂǂ̔c�����@�ɂ��āA�����������������B
����ł́A���ɁA�ƒ�ł̎��g�݂ł����A����22�N�x�̎��тȂǂ��܂Ƃ܂��Ă���A���̏���тȂǂ̔c�����@�ɂ��āA�����������������B
 �ɂ���܂��u�m�[���f�B�A�E�`�������W�v�Ɓu���Q�E���N���E�����͂�v�ɂ��܂��āA���w�Z�ł�1�J���A���w�Z�ł�1�T�Ԃ̏d�_���Ԃ��w�����Ƃɐݒ肵�āA���g�݂̏[����}��܂����B
�ɂ���܂��u�m�[���f�B�A�E�`�������W�v�Ɓu���Q�E���N���E�����͂�v�ɂ��܂��āA���w�Z�ł�1�J���A���w�Z�ł�1�T�Ԃ̏d�_���Ԃ��w�����Ƃɐݒ肵�āA���g�݂̏[����}��܂����B
���̍ہA�d�_���Ԃ̎��g���ʂ��e�����w�Z�̊e�w�N1�w���𒊏o����`�ŏW�v�E���͂��s���܂����B
���̌��ʁA�u�m�[���f�B�A�E�`�������W�v�ł�7���߂������w�����u��9���߂��ɂ̓Q�[���͂��Ȃ��v���ƂɎ��g�݁A�����ȏ�̏����w�����u���Ԃ����߂ăQ�[�������邱�Ɓv��u�e���r�ԑg��I��ł݂�v���ƂɎ��g�߂Ă������Ƃ��c���ł��܂����B
 ����ł́A�w�Z���J���ɃA���P�[�g�������p���āA���т̔c��������Ă���Ǝv���܂����ی�҂̈ӌ����l�X���Ǝv���܂��B�D�ӓI�Ȉӌ��܂��͔ᔻ�I�Ȉӌ������Љ�������B
����ł́A�w�Z���J���ɃA���P�[�g�������p���āA���т̔c��������Ă���Ǝv���܂����ی�҂̈ӌ����l�X���Ǝv���܂��B�D�ӓI�Ȉӌ��܂��͔ᔻ�I�Ȉӌ������Љ�������B
 �ی�҂̊F�l���炨�������������z�����܂��Ɓu�m�[���f�B�A�E�`�������W���̎��g�݂��ӎ����邾���ł������Ԃ����Ă�����̂��Ǝv���܂����v�Ƃ��������z��u�Q�[�������鎞�Ԃ����Ȃ��Ȃ�A�����鎞�Ԃ������A������Ă��܂��B�����Ăق����ł��v�u���R�Ɖ�b�������܂����B�܂��A���ꂩ������g��ł݂����Ǝv���܂��v���邢�́u��������������ɉƎ�����`���Ă���Ă��܂��v�Ƃ��������z�����������Ă��܂��B
�ی�҂̊F�l���炨�������������z�����܂��Ɓu�m�[���f�B�A�E�`�������W���̎��g�݂��ӎ����邾���ł������Ԃ����Ă�����̂��Ǝv���܂����v�Ƃ��������z��u�Q�[�������鎞�Ԃ����Ȃ��Ȃ�A�����鎞�Ԃ������A������Ă��܂��B�����Ăق����ł��v�u���R�Ɖ�b�������܂����B�܂��A���ꂩ������g��ł݂����Ǝv���܂��v���邢�́u��������������ɉƎ�����`���Ă���Ă��܂��v�Ƃ��������z�����������Ă��܂��B
�܂��A�u���Q���N���́A���̒��x�̃`�������W�ł͒��w���̉��P�͓���Ɗ����܂��v�Ƃ��������z��u�m�[���f�B�A�͂ƂĂ�����Ɗ����܂����v�Ƃ������z�Ȃǂ������������Ă���Ƃ���ł��B
 ���ɒn��ł̎��g�݂ł����A���̎��т̔c���͂ǂ̂悤�ɂ��Ă��܂����B�܂����̐��ʂ͂ǂ̂悤�ɕ��͂��Ă܂����B
���ɒn��ł̎��g�݂ł����A���̎��т̔c���͂ǂ̂悤�ɂ��Ă��܂����B�܂����̐��ʂ͂ǂ̂悤�ɕ��͂��Ă܂����B
 �n��ł̎��g�݂ɂ��܂��ẮA�w�K�ӗ~�����߂���A�v�l�͂┻�f�͂��g�ɕt�����肷��悤�ȑ̌��Ƃ��Đ����邱�Ƃ�ڎw���Ă���A�����̐��ʂ𐔒l�I�ɔc������͓̂���Ƃ���ł��B
�n��ł̎��g�݂ɂ��܂��ẮA�w�K�ӗ~�����߂���A�v�l�͂┻�f�͂��g�ɕt�����肷��悤�ȑ̌��Ƃ��Đ����邱�Ƃ�ڎw���Ă���A�����̐��ʂ𐔒l�I�ɔc������͓̂���Ƃ���ł��B
�������Ȃ���A�������k���n��̍s�����ɎQ������ۂɂ́A���E�����q�ǂ������ƂƂ��ɒn��ɓ����āA���ʂ����Ƃ��ė���悤�ɂ��Ă���A�e�w�Z�ɂ͒n���ی�҂���́u�n��̍s����|�������Ɏ������k����������Q�����Ă����悤�ɂȂ����v�Ƃ�������A�u���������C�����悭�ł���悤�ɂȂ����v�Ƃ����������Ă���܂��B
���N�x�̒n��s�����ւ̎������k�̎Q���́A10�������_�ʼn��אl���ŁA��18000���ɏ���Ă���A���łɍ�N�x1�N�Ԃ̎Q���l�����Ă��܂��B�����������Ƃ𐬉ʂƂ��ĂƂ炦�Ă���܂��B
 ���_���u�w�͌���Ɍ�����3�̒Ǝ��g�݁v�ɂ��Ċm�F�����Ă��������܂����B���̒��ł��G��܂������u���сv���ǂ̂悤�ɔc�����邩�Ƃ�����������Ǝv���Ă��܂��B���т��c���ł���A���̂��Ƃ���p���I�ȉ��P�ɂȂ��邩��ł��B
���_���u�w�͌���Ɍ�����3�̒Ǝ��g�݁v�ɂ��Ċm�F�����Ă��������܂����B���̒��ł��G��܂������u���сv���ǂ̂悤�ɔc�����邩�Ƃ�����������Ǝv���Ă��܂��B���т��c���ł���A���̂��Ƃ���p���I�ȉ��P�ɂȂ��邩��ł��B
�u����3�̒Ǝ��g�݁v�́u�w�͌���v�Ɍ��������̂ł��B�܂�A�w�Z�E�ƒ�E�n��ł̎��g�݂̌��ʁA�������k�̊w�͂̌��オ�}���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B
�����Ŏ���ł����A���g�݂̌��ʊw�͌��オ�ǂ̂��炢�}��ꂽ�̂��A�ǂ̂悤�ɔc���E�m�F���Ă���̂����q�˂������܂��B�Ƃ����̂��A�u�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ���v����́u�w�͌���Ɍ�����3�̒Ǝ��g�݁v�͕���19�N�x������{����Ă���u�S���w�́E�w�K�����v�̌��ʂ��x�[�X�ɂȂ��Ă�����̂Ɨ������Ă��܂��B�{�N�x�����̈ϑ����ƂŁu�q�ǂ��̗̑͌���x�����Ɓv�����{����܂����A�̗͌���ɂ��Ă̗͑͑���Ŕc�����\�ł��B�u�S���w�́E�w�K�����v�ɂ��ẮA����22�N�x����͑S�Z���{�ł͂Ȃ��Ȃ�A��3���̒��o�ƂȂ�A���{��]�̗L�����̎��O�m�F������Ă��邩�Ǝv���܂��B
23�N�x�́A�����{��k�Ђ̉e����4��19���ɗ\�肳��Ă�������������߂ƂȂ�܂����B�����������Ƃ܂Ők�Ђ̉e�����o�Ă���Ƃ������ł����A�������ɂ��ẮA����9�����{�ɋ���ψ����ʂ��Ĕz�z�̈ӌ������A��]�����w�Z�ɔz�z�����Ƃ������ł����A��]���������܂߁A���������������B
 �܂��A���g�݂̐��ʂƂ��Ă̊w�͌���ł����A��̑��ʂƂ���23�N�x�̍�ʌ��w�K�����̌��ʂ��݂܂��ƁA�����ނˌ����ςƓ��l�������͕��ς��Ă���A��N�x�Ɣ�r���Č��サ�Ă���܂��B�������́A�{�����̌��ʂ̈�ł���A���g�݂̐��ʂ̔c���ɂ��܂��ẮA�e��w�͒������n�߁A�e�w�Z�ł̒���e�X�g�A�܂����X�̊w�K�ւ̎��g�ݏ�����������I�ɂƂ炦��悤�ɂ��Ă���܂��B
�܂��A���g�݂̐��ʂƂ��Ă̊w�͌���ł����A��̑��ʂƂ���23�N�x�̍�ʌ��w�K�����̌��ʂ��݂܂��ƁA�����ނˌ����ςƓ��l�������͕��ς��Ă���A��N�x�Ɣ�r���Č��サ�Ă���܂��B�������́A�{�����̌��ʂ̈�ł���A���g�݂̐��ʂ̔c���ɂ��܂��ẮA�e��w�͒������n�߁A�e�w�Z�ł̒���e�X�g�A�܂����X�̊w�K�ւ̎��g�ݏ�����������I�ɂƂ炦��悤�ɂ��Ă���܂��B
�S���w�́E�w�K�����̖����q���ɂ��܂��ẮA�e�w�Z�̊�]�ɉ����A�z�z�������܂����B
 ��ʌ��w�K�����A�e��w�͒�����w�Z�̒���e�X�g�Ŋm�F���Ă���Ƃ������ł����A��ʌ��w�K�����ł͑Ώۂ����w5�N���ƒ��w2�N���ŁA�u�S���w�́E�w�K�����v�Ɏ����ẮA���N�Ώۂ��ς��܂��B
��ʌ��w�K�����A�e��w�͒�����w�Z�̒���e�X�g�Ŋm�F���Ă���Ƃ������ł����A��ʌ��w�K�����ł͑Ώۂ����w5�N���ƒ��w2�N���ŁA�u�S���w�́E�w�K�����v�Ɏ����ẮA���N�Ώۂ��ς��܂��B
�����ŁA�w�щ��P�v���W�F�N�g�ł́A����ǂ̂悤�Ȏ��g�݂��s���Ă����̂��B�܂��A3�̒Ǝ��g�݂̎��т܂��A����ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����̂��A���璷�̂��l���������������������B
 �{�s�́u�w�щ��P�v���W�F�N�g�v�͒n��E�ƒ�E�w�Z�̎O�҂��������ŁA�s�������Ďq�ǂ������̊w�͌���̂��߂̊�ՂÂ������w���i���Ă������Ƃł��B
�{�s�́u�w�щ��P�v���W�F�N�g�v�͒n��E�ƒ�E�w�Z�̎O�҂��������ŁA�s�������Ďq�ǂ������̊w�͌���̂��߂̊�ՂÂ������w���i���Ă������Ƃł��B
����2�N�ԂŁA��1�̒ł���1���Ԃ̎��Ƃ̖ڕW�̖��m���ɂ��ẮA�啪�蒅���Ă��܂����B�������^���ł��A�s���S��E�n�悲�Ƃɐi��ł���A���|�����E�{�����e�B�A�����A���������Ȃǂɂ������̏����w�����Q�����A�����ɐi��ł��Ă���Ƃ���ł��B
����ɁA���N�x��16�Z�̏����w�Z�Ɂu����s�w�щ��P�v���W�F�N�g���i���Ɓv���f���Z�̌����ϑ����s���Ă���A����3�N�ԂŎs���S�Z�Ɍ������ϑ�����v��ł���܂��B
�{���Ƃ�����ɐ��i���A�q�ǂ������̐�������w�����o����A�q�ǂ���������сA�s���ɐM������鏊��s�̋��炪�i��ł������̂ƍl���Ă���܂��B
 ���̎��g�݂��p�����Ă����Ƃ̂��Ƃł����A����w�щ��P�v���W�F�N�g�̌������ɓ������ẮA�w�͌���Ɍ��������ʓI�Ȏ��g�݂͂ǂ̂悤�Ȏ����K�v���͂������ł����A���т��ǂ̂悤�ɔc�����Ă������A�Ƃ��������Ƃɂ��Ă��������Ă����ׂ��Ǝv���܂����A���璷�̂��l���������������������B
���̎��g�݂��p�����Ă����Ƃ̂��Ƃł����A����w�щ��P�v���W�F�N�g�̌������ɓ������ẮA�w�͌���Ɍ��������ʓI�Ȏ��g�݂͂ǂ̂悤�Ȏ����K�v���͂������ł����A���т��ǂ̂悤�ɔc�����Ă������A�Ƃ��������Ƃɂ��Ă��������Ă����ׂ��Ǝv���܂����A���璷�̂��l���������������������B
 ���т̔c���ɂ��܂��ẮA�w�Z�E�ƒ�E�n�悻���Ď������k���g�����ʂ������ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł��̂ŁA�e�s�̎��g�ݓ��e�ɉ����܂��āA���l��ʐ^���邢�͊��z���ɂ��A���ʂ𑽖ʓI�ɔc������ƂƂ��ɁA16�Z�̌������ʂ��܂߂܂��āA�������킩��₷���j������@�ɂ��Č������Ă܂��肽���ƍl���܂��B���̂��Ƃɂ��܂��Ă��A�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ�����������肢�������Ǝv���܂��B
���т̔c���ɂ��܂��ẮA�w�Z�E�ƒ�E�n�悻���Ď������k���g�����ʂ������ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł��̂ŁA�e�s�̎��g�ݓ��e�ɉ����܂��āA���l��ʐ^���邢�͊��z���ɂ��A���ʂ𑽖ʓI�ɔc������ƂƂ��ɁA16�Z�̌������ʂ��܂߂܂��āA�������킩��₷���j������@�ɂ��Č������Ă܂��肽���ƍl���܂��B���̂��Ƃɂ��܂��Ă��A�w�щ��P�v���W�F�N�g�ψ�����������肢�������Ǝv���܂��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 �w�K�x�����ɂ���
�w�K�x�����ɂ���
���ɁA�w�K�x�����ɂ��āA���q�˂������܂��B���̎�����A��قǂ̎���ɑ����A�q�ǂ������̊w�͌����}��ϓ_����s���܂��B����ł́A�w�Z���畔���ɉ��_���f���܂��B
 �͂��߂ɁA���݂̊w�K�x�����̔z�u�ɂ��Ă��������������B
�͂��߂ɁA���݂̊w�K�x�����̔z�u�ɂ��Ă��������������B
 ���E���w�Z�A�e�Z1���Ōv47���̔z�u�ł��B
���E���w�Z�A�e�Z1���Ōv47���̔z�u�ł��B
 ���ɁA�w�K�x�����́A���ʂȎ��i���K�v�ł����B
���ɁA�w�K�x�����́A���ʂȎ��i���K�v�ł����B
 �����Ƃ��āA���w�Z�܂��͒��w�Z�̋����̎��i��L����l�Ƃ��Ă���܂��B
�����Ƃ��āA���w�Z�܂��͒��w�Z�̋����̎��i��L����l�Ƃ��Ă���܂��B
 ����ł́A���݁A����s�ɂ����Ă͊w�K�x�����ƌĂ�ł��܂����A����ȑO�́A�����⏕���ƌĂ�ł������Ƃ��������Ǝv���܂����A����܂ł̔z�u���тɂ��āA�o�ܓ����܂ߊȌ��ɂ��������������B
����ł́A���݁A����s�ɂ����Ă͊w�K�x�����ƌĂ�ł��܂����A����ȑO�́A�����⏕���ƌĂ�ł������Ƃ��������Ǝv���܂����A����܂ł̔z�u���тɂ��āA�o�ܓ����܂ߊȌ��ɂ��������������B
 ����14�N�ɁA�����Ȋw�ȁu�w�Z���������v�����v�ً}�n��ٗp�n�o���ʌ�t���̕⏕�āA�����⏕���Ƃ��āA103����z�u���܂����B15�N�ɂ�119����z�u���܂����B
����14�N�ɁA�����Ȋw�ȁu�w�Z���������v�����v�ً}�n��ٗp�n�o���ʌ�t���̕⏕�āA�����⏕���Ƃ��āA103����z�u���܂����B15�N�ɂ�119����z�u���܂����B
���̌�A����16�N�ɍ��̕⏕���I�����A20�N����͊w�K�x�����Ƃ��Ĕz�u���Ă���܂��B20�N����͓��ʎx������x�������V���ɔz�u���ꂽ���Ƃ�����A23�N�x�́A47���̔z�u�ƂȂ��Ă���܂��B
 ����ł́A�Ȃ��A����47�l�Ŋe�Z1���z�u�ƂȂ����̂��A���̗��R�������������������B
����ł́A�Ȃ��A����47�l�Ŋe�Z1���z�u�ƂȂ����̂��A���̗��R�������������������B
 ����20�N����́A���ʎx������x�������A�V���ɑS�Z�ɔz�u�������ƁA�܂��{�N�x����́A���w�Z�O���ꊈ���x����14����z�u����ȂǁA�]���̊w�K�x�����̋@�\�̈ꕔ��V�����`�̎x�����Ƃ��āA�w�Z�̎x�����s���Ă��邽�߁A���݂�47���Ŋe�Z1���̔z�u�ƂȂ��Ă���܂��B
����20�N����́A���ʎx������x�������A�V���ɑS�Z�ɔz�u�������ƁA�܂��{�N�x����́A���w�Z�O���ꊈ���x����14����z�u����ȂǁA�]���̊w�K�x�����̋@�\�̈ꕔ��V�����`�̎x�����Ƃ��āA�w�Z�̎x�����s���Ă��邽�߁A���݂�47���Ŋe�Z1���̔z�u�ƂȂ��Ă���܂��B
 ���ʎx�����ʎx�������e�Z�ɔz�u���邱�ƂƂȂ������߂Ƃ������Ƃł��B�m���ɁA���ʂȎx�����K�v�Ȏ������k������܂��̂ŁA���ʎx������x�����̔z�u�͏d�v�ƍl���܂��B�����āA���w�Z�ł́A�V���ɊO���ꊈ�������ƂƂ��Ďn�܂�A�O���ꊈ���x�����̔z�u���s���A�S�̂Ƃ��Ė{���Ɏ�����x�����̔z�u���Ǝv���Ă���܂��B�����Ŋw�K�x�����w�K�x�����̔z�u���ʂ��ǂ̂悤�ɕ��͂��Ă��܂����B
���ʎx�����ʎx�������e�Z�ɔz�u���邱�ƂƂȂ������߂Ƃ������Ƃł��B�m���ɁA���ʂȎx�����K�v�Ȏ������k������܂��̂ŁA���ʎx������x�����̔z�u�͏d�v�ƍl���܂��B�����āA���w�Z�ł́A�V���ɊO���ꊈ�������ƂƂ��Ďn�܂�A�O���ꊈ���x�����̔z�u���s���A�S�̂Ƃ��Ė{���Ɏ�����x�����̔z�u���Ǝv���Ă���܂��B�����Ŋw�K�x�����w�K�x�����̔z�u���ʂ��ǂ̂悤�ɕ��͂��Ă��܂����B
 �w�Z�̏ɉ����āA����̊w����w�N�A���邢�͒��w�Z�ɂ����܂��ẮA���w�≹�y�ȂǓ���̋��ȂɊw�K�x���������邱�Ƃɂ��A��肫�ߍׂ₩�ȏ��l���w�����\�ɂȂ�����A�ʑΉ����K�v�Ȏ����ɑ���w������葽���ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��B�܂��A�����Ɗw�K�x�������Ƃ��Ɋw�K�w������w���ɓ��邱�Ƃɂ��A�������k��l��l�ɉ������w�����ł��A���ʂ������Ă���Ƃ���ł��B
�w�Z�̏ɉ����āA����̊w����w�N�A���邢�͒��w�Z�ɂ����܂��ẮA���w�≹�y�ȂǓ���̋��ȂɊw�K�x���������邱�Ƃɂ��A��肫�ߍׂ₩�ȏ��l���w�����\�ɂȂ�����A�ʑΉ����K�v�Ȏ����ɑ���w������葽���ł���悤�ɂȂ��Ă���܂��B�܂��A�����Ɗw�K�x�������Ƃ��Ɋw�K�w������w���ɓ��邱�Ƃɂ��A�������k��l��l�ɉ������w�����ł��A���ʂ������Ă���Ƃ���ł��B
 �x�����̌��ʂ͑傫���Ƃ������ł����A�ی�҂܂��͎������k�A����ɂ͈ꏏ�Ɏ��Ƃ�i�߂Ă���搶���̔����⊴�z�Ƃ��������̂͂������ł����B
�x�����̌��ʂ͑傫���Ƃ������ł����A�ی�҂܂��͎������k�A����ɂ͈ꏏ�Ɏ��Ƃ�i�߂Ă���搶���̔����⊴�z�Ƃ��������̂͂������ł����B
 �������k����́A�����̃y�[�X�ɍ��������ŋ����Ă�����Ċ����������B�x�ݎ��ԂɌl�I�ɋ����Ă�����Ċ����������Ȃǂ̊��z���������܂��B�ی�҂�����w�K�x�����ɑ��čm��I�Ȉӌ������������Ă���܂��B
�������k����́A�����̃y�[�X�ɍ��������ŋ����Ă�����Ċ����������B�x�ݎ��ԂɌl�I�ɋ����Ă�����Ċ����������Ȃǂ̊��z���������܂��B�ی�҂�����w�K�x�����ɑ��čm��I�Ȉӌ������������Ă���܂��B
�w�Z������A�����̎�̓͂��Ȃ��Ƃ���ւ̎x�����ł���Ƃ������_��A�s�o�Z�����ւ̊w�K�x���Ƃ��āA�ʂɑΉ��������ƂŁA�w���ɕ��A�ł������������Ă���܂��B
 ����ł́A�w�K�x�����ɂ��w�͌���ɑ�����ʂ���т��̔c���́A�ǂ̂悤�ɍs���Ă��܂����B
����ł́A�w�K�x�����ɂ��w�͌���ɑ�����ʂ���т��̔c���́A�ǂ̂悤�ɍs���Ă��܂����B
 �w�K�x�����̕]���ɂ��܂��ẮA�e�w�Z�Ɋw�K�x�����̊��p�����̕��˗����A�ǂ̊w�Z�ɂ����܂��Ă��������Ă���Ƃ̉����������Ă���܂��B�w�K�x���������邱�Ƃɂ��A��肫�ߍׂ������l���w�����\�ɂȂ�����A�ʑΉ����K�v�Ȏ������k�ɑ���w������葽���ł���p�ɂȂ����肷�邱�Ƃ���A�������k�̊w�K�ӗ~�����܂�����w�K�ɑ��鎩�M������Ȃǂ̕ϗe�������A�����̎�̓͂��ɂ����Ƃ���ւ̎x�����ł���Ƃ����_�ŁA���ʂ��o�Ă���Ǝ~�߂Ă���܂��B
�w�K�x�����̕]���ɂ��܂��ẮA�e�w�Z�Ɋw�K�x�����̊��p�����̕��˗����A�ǂ̊w�Z�ɂ����܂��Ă��������Ă���Ƃ̉����������Ă���܂��B�w�K�x���������邱�Ƃɂ��A��肫�ߍׂ������l���w�����\�ɂȂ�����A�ʑΉ����K�v�Ȏ������k�ɑ���w������葽���ł���p�ɂȂ����肷�邱�Ƃ���A�������k�̊w�K�ӗ~�����܂�����w�K�ɑ��鎩�M������Ȃǂ̕ϗe�������A�����̎�̓͂��ɂ����Ƃ���ւ̎x�����ł���Ƃ����_�ŁA���ʂ��o�Ă���Ǝ~�߂Ă���܂��B
�܂��A�e�w�Z�̊����̗l�q�ɂ��܂��ẮA���ɂ܂Ƃ߂����Ă��������Ă���܂��B
 ���͎����S���q�ǂ��������������đ�l�ɂȂ�A�ƒ�������Ă��A����s�Ɉ��������Z��ł������������Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂ɂ́A�q�ǂ��������f���炵�����������悤�ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ��A�������̈�ł���Ǝv���Ă܂����A���ꂪ�u����u�����h�v�ɂ��Ȃ���Ǝv���Ă܂��B�����āA�����������Ƃ��s�����ɂ��A���s���珊��s�Ɉڂ�Z��ł����������X����������肪�����Ǝv���Ă��܂��B�����ŁA����w�K�x�����𑝂₷�l�������邩�A���璷�ɂ��q�˂������܂��B
���͎����S���q�ǂ��������������đ�l�ɂȂ�A�ƒ�������Ă��A����s�Ɉ��������Z��ł������������Ǝv���Ă��܂��B���̂��߂ɂ́A�q�ǂ��������f���炵�����������悤�ȏ�Ԃɂ��邱�Ƃ��A�������̈�ł���Ǝv���Ă܂����A���ꂪ�u����u�����h�v�ɂ��Ȃ���Ǝv���Ă܂��B�����āA�����������Ƃ��s�����ɂ��A���s���珊��s�Ɉڂ�Z��ł����������X����������肪�����Ǝv���Ă��܂��B�����ŁA����w�K�x�����𑝂₷�l�������邩�A���璷�ɂ��q�˂������܂��B
 ���l���w���ɂ�����鍑�̓�����A���ʎx������x�����A�S�̂ӂꂠ�����k���A�w�Z�����c���̒n��̃{�����e�B�A�ɂ��x���̏܂��A�o�����X�̂Ƃꂽ�x����i�߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B
���l���w���ɂ�����鍑�̓�����A���ʎx������x�����A�S�̂ӂꂠ�����k���A�w�Z�����c���̒n��̃{�����e�B�A�ɂ��x���̏܂��A�o�����X�̂Ƃꂽ�x����i�߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B
 ����ł́A�s���Ɏf���܂��B�������I�������Ă��������Ă���A2���̐e�䂳��w���̃N���X��\�͕ʁE�w�͕ʂ̃N���X�Ґ��ɂł��Ȃ��̂��q�˂��܂����B�Ƃ����̂��q�ǂ����w�Z�̎��Ƃɂ��Ă������A�����āA�m�ɍs���Ă����Ă����Ȃ��̂Łu���Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��v�u���Ƃ��H�v���Ă��炦�Ȃ����v�Ƃ������̂ł����B
����ł́A�s���Ɏf���܂��B�������I�������Ă��������Ă���A2���̐e�䂳��w���̃N���X��\�͕ʁE�w�͕ʂ̃N���X�Ґ��ɂł��Ȃ��̂��q�˂��܂����B�Ƃ����̂��q�ǂ����w�Z�̎��Ƃɂ��Ă������A�����āA�m�ɍs���Ă����Ă����Ȃ��̂Łu���Ƃ��Ȃ�Ȃ����̂��v�u���Ƃ��H�v���Ă��炦�Ȃ����v�Ƃ������̂ł����B
�����ŁA�o�����X�̂Ƃꂽ�x���͕K�v���Ǝv���܂����A�ł���A�����́A�w�K�x�����̑啝�ȑ������ł��Ȃ����s���ɂ��������܂��B
 �B���{��̋������ڎw���ϓ_������A���̊w�K�x�������Ƃɂ��܂��Ă��A�l�X�Ȏx���̏��ӂ܂��Ȃ���A����Ȃ�g�[��}���悤����ψ���ɓ��������Ă܂���܂��B
�B���{��̋������ڎw���ϓ_������A���̊w�K�x�������Ƃɂ��܂��Ă��A�l�X�Ȏx���̏��ӂ܂��Ȃ���A����Ȃ�g�[��}���悤����ψ���ɓ��������Ă܂���܂��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 ����n��̈�ِ����ɂ���
����n��̈�ِ����ɂ���
���ɁA����n��̈�ِ����ɂ��āA�������˂������܂��B���̎���ɂ��ẮA���͕���21�N3���c��ōs���܂����B���̌㏊��n��̋c�������x�����₵�܂������A���߂Ď��₳���Ă��������܂��B
�͂��߂ɁA����܂ł̌o�߂ł����A����n��̈�قɂ��Ă͕���18�N12���̋c��ɂ����āA����ґ�7940�������o���ꂽ����u����n��̈�ق����݊肢�������v���S���v�ō̑�����A������ĕ���20�N4���ɂ͎s���ɑ��Ē�����̊F�l�����߂ėv�]���o���Ă���܂��B
����21�N3���c��ŁA�s���ɑ��ėv�]��ǂ̂悤�Ɍ����������Ɍ����ǂ̂悤�Ȏ��g�݂��s�������A�i�����܂ߍ���݂̂Ƃ����ɂ��Ă����������Ƃ���A�u����ψ���𒆐S�ɁA����܂�5�n��ɐ������Ă܂���܂����n��̈�ق̋K�͂�{�ݓ��e����ɁA����n��ɂӂ��킵���̈�ِ����ɓK���Ȑݒu�ꏊ��\�����e�A������p�̎Z�o���A����������i�߂Ă��Ă���ł���A�����Ȃǂ����邪�A���������֘A�c�̂�n��Z���̂��v�]�����������Ȃ���A�ł�����葁���̏���n��̈�ق̐����ɓw�͂��Ă܂��肽���ƍl���Ă���v�Ƃ̓��ق�����܂����B
���̓��ق܂��A�m�F�����܂ߋ��瑍�������ɉ��_���f���܂�
 ��ɉ������ꂽ�u����s�X�|�[�c�U���v��v�ɂ����āA�n��̈�ق͂ǂ̂悤�Ȉʒu�Â��ƂȂ��Ă��܂����B
��ɉ������ꂽ�u����s�X�|�[�c�U���v��v�ɂ����āA�n��̈�ق͂ǂ̂悤�Ȉʒu�Â��ƂȂ��Ă��܂����B
 ����s�X�|�[�c�U���v�悾���R�͂ɂ����܂��āA���U�ɂ킽���ăX�|�[�c���y���߂�悤�A�s���̎�̓I�ȃX�|�[�c�������x�����Ă������߁A���ݒn��̈��5�ق������قɕ��݂���Ă���܂��B�i�x���A�V����A����w�A�����A�O�����j�@�@���瑍������
����s�X�|�[�c�U���v�悾���R�͂ɂ����܂��āA���U�ɂ킽���ăX�|�[�c���y���߂�悤�A�s���̎�̓I�ȃX�|�[�c�������x�����Ă������߁A���ݒn��̈��5�ق������قɕ��݂���Ă���܂��B�i�x���A�V����A����w�A�����A�O�����j�@�@���瑍������
 ���ɁA����n��̈�قɂ��ẮA�v��ł͂ǂ̂悤�ȋL�q�ƂȂ��Ă��܂����B
���ɁA����n��̈�قɂ��ẮA�v��ł͂ǂ̂悤�ȋL�q�ƂȂ��Ă��܂����B
 ����n��̈�فi�����n��̈�فj�ɂ��܂��Ắu����������ݒu�ꏊ�A�H�����@�A������p�Ȃǂ𑍍��I�Ɍ����v�ƂȂ��Ă���܂��B�@�@���瑍������
����n��̈�فi�����n��̈�فj�ɂ��܂��Ắu����������ݒu�ꏊ�A�H�����@�A������p�Ȃǂ𑍍��I�Ɍ����v�ƂȂ��Ă���܂��B�@�@���瑍������
 ����21�N9���ɒ����ōs�����u�s�L�{�ݓ��̗L�����p�Ɋւ��闘�p��]�ɂ��āv�̒����ŁA����ψ���͕�����ِՒn�ɂ��Ēn��̈�ِ����Ɋ��p�������|�̉��s���Ă��܂����A������Ւn���p�ɂ��Ă̌������s�����̂��B�܂���̓I�ɁA���݂̕�����ق͂ǂ����Ă����̂��B���������Ɏf���܂��B
����21�N9���ɒ����ōs�����u�s�L�{�ݓ��̗L�����p�Ɋւ��闘�p��]�ɂ��āv�̒����ŁA����ψ���͕�����ِՒn�ɂ��Ēn��̈�ِ����Ɋ��p�������|�̉��s���Ă��܂����A������Ւn���p�ɂ��Ă̌������s�����̂��B�܂���̓I�ɁA���݂̕�����ق͂ǂ����Ă����̂��B���������Ɏf���܂��B
 ����21�N9���ɖ����p�n���̗��p��]�ɂ��Ă̒����ɂ����āA�X�|�[�c�U���ۂ��當����ِՒn������n��̈�ٌ��ݗp�n�̌��n�Ƃ��Č����������|�̉�����A����21�N10��29���̎s�L�����p�����ψ���Œ������ʂ���Ă�����̂ł��B
����21�N9���ɖ����p�n���̗��p��]�ɂ��Ă̒����ɂ����āA�X�|�[�c�U���ۂ��當����ِՒn������n��̈�ٌ��ݗp�n�̌��n�Ƃ��Č����������|�̉�����A����21�N10��29���̎s�L�����p�����ψ���Œ������ʂ���Ă�����̂ł��B
���̒����i�K�ɂ����ẮA���p�̊�]�ł���A�����̒�ɋ���ψ���ɂ����ď���n��̈�ق̌��n���m�肵����A�u�s�L�n���擾���p�����ψ���v�ψ���ɑ��ĐR�c�̈˗����Ȃ������̂ł����A���݂܂ŐR�c�̈˗����Ȃ����̂ł������܂��B
 ����ł́A�s�̎{��Ƃ��ĕ�����ِՒn���ǂ̂悤�ɂ���̂��A���̌������s���Ă���̂��B�������������ɂ��������܂��B
����ł́A�s�̎{��Ƃ��ĕ�����ِՒn���ǂ̂悤�ɂ���̂��A���̌������s���Ă���̂��B�������������ɂ��������܂��B
 ������ِՒn�ɂ��܂��ẮA���݂̂Ƃ����̓I�Ȋ��p���܂��Ă���܂���B
������ِՒn�ɂ��܂��ẮA���݂̂Ƃ����̓I�Ȋ��p���܂��Ă���܂���B
�������Ȃ���A��4���s�����v��j�ł͎s�L���Y�̗L�����p���f�����Ă���܂��̂ŁA������ِՒn���p�ɂ��܂��Ă����ʓI�Ȋ��p���@����������K�v���������܂��B
�܂�������ق̌����ɂ��܂��ẮA����ȕ��@�ɂ�茚�z����Ă���܂��̂ŁA��݂̂̂��s������̂ł͂Ȃ��A�{�ݐ����ƈ�̂ōs�����ɂ��A�o��ʂł̌y�����}������̂ƍl���Ă���܂��B
����A������ِՒn���p�ɂ��܂��ẮA�s���j�[�Y�̏\���Ȕc���ɓw�߂�ƂƂ��ɁA�{�݂̐������s���ꍇ�ɂ͌��{�݂̉�̔�p�y���ƐV���Ȏ{�݂ɂ�����܂��ێ��Ǘ���̌��������������Ȃ���A�����I�Ɍ������Ă��������Ǝv���܂��B
 ����ł́A���瑍�������Ɏf���܂����A����ψ���ł͂ǂ̂悤�Ȍ������s���܂������B
����ł́A���瑍�������Ɏf���܂����A����ψ���ł͂ǂ̂悤�Ȍ������s���܂������B
 ����܂łɊ���5�ق��Q�l�ɂ��āA����ɒn��̈�ق�P�ƂŐ��������ꍇ�A�{�K�͂Ƃ��Ă̓o�X�P�b�g�{�[���R�[�g��1�ʁA�o���[�{�[���R�[�g��2�ʁA�o�g�~���g���R�[�g��4�ʂ̍L���A�����ʐςł͂P�Q�O�O�u�قǁA�{�ݓ��e�̓A���[�i�ɍX�ߎ��A�g�C����z�肵�A�T�Z���ݔ�p��2��5�疜�~�Ȃǂ̌��������Ă܂���܂����B
����܂łɊ���5�ق��Q�l�ɂ��āA����ɒn��̈�ق�P�ƂŐ��������ꍇ�A�{�K�͂Ƃ��Ă̓o�X�P�b�g�{�[���R�[�g��1�ʁA�o���[�{�[���R�[�g��2�ʁA�o�g�~���g���R�[�g��4�ʂ̍L���A�����ʐςł͂P�Q�O�O�u�قǁA�{�ݓ��e�̓A���[�i�ɍX�ߎ��A�g�C����z�肵�A�T�Z���ݔ�p��2��5�疜�~�Ȃǂ̌��������Ă܂���܂����B
�����������ŋc���̂�����ɂ�����܂����A21�N9���̎s�L�{�݂̗L�����p�Ɋւ��闘�p��]�ɂ��āv�̒����ɂ����āA������ِՒn�����p�������|�������̂ł������܂��B
 �������S�̖�������܂��̂ŁA�����ǂ��ɂ��Ȃ邱�Ƃł͂Ȃ����Ƃ͂킩��܂����A��̓I�Ȍ����Ȃ�����ЂƂ��i�߂Ă������������Ǝv���܂����A����ψ���Ƃ��Ă͍���ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����l�������瑍�������A�����������������B
�������S�̖�������܂��̂ŁA�����ǂ��ɂ��Ȃ邱�Ƃł͂Ȃ����Ƃ͂킩��܂����A��̓I�Ȍ����Ȃ�����ЂƂ��i�߂Ă������������Ǝv���܂����A����ψ���Ƃ��Ă͍���ǂ̂悤�ɐi�߂Ă����l�������瑍�������A�����������������B
 ����ł����A�X�|�[�c���i�R�c��A����ψ����c�ł̐R�c�A�������͂��߂Ƃ��āA�s�����ǂƂ̒�������v��s�̒�����}���Ă����킯�ł������܂����A�{�ݐ����͑�^���ƂƂȂ�܂��̂ŁA���������Ă��S���I�Ȓ�����Ƃ������ɍs���Ă��������ۑ肾�ƍl���܂��B
����ł����A�X�|�[�c���i�R�c��A����ψ����c�ł̐R�c�A�������͂��߂Ƃ��āA�s�����ǂƂ̒�������v��s�̒�����}���Ă����킯�ł������܂����A�{�ݐ����͑�^���ƂƂȂ�܂��̂ŁA���������Ă��S���I�Ȓ�����Ƃ������ɍs���Ă��������ۑ肾�ƍl���܂��B
 ����ł́A�s���Ɏf���܂��B�`���\���グ�܂������A�O�s���́u�ł�����葁���̏���n��̈�ق̐����ɓw�͂��Ă܂��肽���ƍl���Ă���v�|�̓��ق�����Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA����n��̐l���͖�3���l�ł��B�s�̒��S�X�Ƃ��Č����k�n��̍ĊJ�����Ƃŗ��h�Ȍ����ٓ����ł����킯�ł����A���X�X���܂ߋ����n�悪���C�ɂȂ邱�ƂŁA����s�S�̂̊��������}����Ǝv���Ă���܂��B����n��̈�ق̐����ɑ���s���̂��l���������������������B
����ł́A�s���Ɏf���܂��B�`���\���グ�܂������A�O�s���́u�ł�����葁���̏���n��̈�ق̐����ɓw�͂��Ă܂��肽���ƍl���Ă���v�|�̓��ق�����Ă��܂��B���Ȃ݂ɁA����n��̐l���͖�3���l�ł��B�s�̒��S�X�Ƃ��Č����k�n��̍ĊJ�����Ƃŗ��h�Ȍ����ٓ����ł����킯�ł����A���X�X���܂ߋ����n�悪���C�ɂȂ邱�ƂŁA����s�S�̂̊��������}����Ǝv���Ă���܂��B����n��̈�ق̐����ɑ���s���̂��l���������������������B
 ����18�N12���s�c��ŁA7940�l���琿�肪�o����A�S���v�ō̑�����Ă��邱�ƁA���������ٗ��ւ��̒��ŁA�̈�ِ������������ꂽ���A���ۑ�ɂ��f�O�����o�܂����邱�ƁA����n��ɂ��Z�܂��̑����̕������̒��N�̔O��ł���A���̒n��̊������̂��߂ɂ��A���Ƃ��Ă͂Ȃ�ׂ������̌��ݐ��i�Ɍ����āA�w�߂Ă��������ƍl���܂��B
����18�N12���s�c��ŁA7940�l���琿�肪�o����A�S���v�ō̑�����Ă��邱�ƁA���������ٗ��ւ��̒��ŁA�̈�ِ������������ꂽ���A���ۑ�ɂ��f�O�����o�܂����邱�ƁA����n��ɂ��Z�܂��̑����̕������̒��N�̔O��ł���A���̒n��̊������̂��߂ɂ��A���Ƃ��Ă͂Ȃ�ׂ������̌��ݐ��i�Ɍ����āA�w�߂Ă��������ƍl���܂��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 �X�H����LED���E�h�Ƒ�ɂ���
�X�H����LED���E�h�Ƒ�ɂ���
�ߓd���ʂ����҂ł���X�H����LED���ɂ��Ă��q�˂��܂��B
 �s���Ǘ�����X�H���͎s���ɂ�������܂����B�܂����̔N�Ԃ̓d�C�g�p�ʂ◿���͂ǂ̂��炢�ɂȂ�̂��A���������܂��B
�s���Ǘ�����X�H���͎s���ɂ�������܂����B�܂����̔N�Ԃ̓d�C�g�p�ʂ◿���͂ǂ̂��炢�ɂȂ�̂��A���������܂��B
 ����23�N4��1�����݁A9887���ł������܂��B
����23�N4��1�����݁A9887���ł������܂��B
�N�Ԃ̓d�C�g�p�ʂ̂����ẮA����22�N�x�́A���Z�z�łU�R�Q�P���X�O�P�T�~�ł������܂��B�Q�R�N�x�͗\�Z�z�łU�U�P�W���ł������܂��B
�d�C����ʂɂ��܂��ẮA���H�Ɩ����ɂ����܂��Ă͂��̂قƂ�ǂ��d�C�����x���敪������d�͂ɒ�߂��Ă���u���O�X�H��A�v�ƂȂ��Ă���܂��B�����������Ƃ���A�d�C�g�p�ʂ̔c���͂ł��Ȃ��ɂ������܂��B
 ���̂����ALED�����g�p�������̂͂�������܂����B�܂����̂��ׂĂ����̂��ׂĂ�LED�������ꍇ�̔�p�y�ѓd�C���������Z�������Ƃ͂���܂����B����ꍇ�ɂ͂��̋��z�����������������B
���̂����ALED�����g�p�������̂͂�������܂����B�܂����̂��ׂĂ����̂��ׂĂ�LED�������ꍇ�̔�p�y�ѓd�C���������Z�������Ƃ͂���܂����B����ꍇ�ɂ͂��̋��z�����������������B
 LED�Ɩ����ɂ��܂��Ă͋c�����ē��̒ʂ�A�Ⴂ����d�͂ŏ]���̏Ɩ����Ɠ����̖��邳�ƂȂ邽�߁A�ߓd���ʂɂ͑�ϗD��Ă���܂��āACO2�r�o�ʂ̍팸�ɂ��Ȃ���A���ɂ��D�����Ɩ����ł������܂��B
LED�Ɩ����ɂ��܂��Ă͋c�����ē��̒ʂ�A�Ⴂ����d�͂ŏ]���̏Ɩ����Ɠ����̖��邳�ƂȂ邽�߁A�ߓd���ʂɂ͑�ϗD��Ă���܂��āACO2�r�o�ʂ̍팸�ɂ��Ȃ���A���ɂ��D�����Ɩ����ł������܂��B
�܂��ALED�Ɩ����̐��ł�����23�N4��1�����݁A�X�W�W�V���̂���LED���͂U�T���ł����B���N�x�łU�T�������Q�R�N�P�Q���P�����݂łP�R�O��LED����ݒu���Ă���܂��B
���ׂĂ̓��H�Ɩ�����LED�ɂ����ꍇ�̌�����p�y�ѓd�C�����ł����A������p�ɂ��Ă͂����悻�P�O���P�O�O�O���~�̔�p�������܂�܂��B
�d�C�����ɂ��܂��Ă͔N�Ԃ����悻�R�S�T�X���V��~�̔�p��������Ǝv���܂��B
 ���ɁA��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂��B�����́u���ꑋ���_�v�������m�ł����B�����m�̏ꍇ�͂��̊T�v��[�I�ɂ��������������B
���ɁA��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂��B�����́u���ꑋ���_�v�������m�ł����B�����m�̏ꍇ�͂��̊T�v��[�I�ɂ��������������B
 �u���ꑋ���_�v�́u�����̑�������Ă���̂���u���Ă���ƁA�O�����炻�̌����͊Ǘ�����Ă��Ȃ��ƔF������A�₪�đ��̑������ׂĔj��A������r���S�̂��r�p���邱�ƂŁA����ɂ��̒n�悪�r��Ă��܂��v�Ƃ����l�����ŁA�����Ȕƍ߂̉�����������Ώ����Ă������ƂŁA�n��S�̂����S���ĕ�点��n���ۂƂ������̂ł��B
�u���ꑋ���_�v�́u�����̑�������Ă���̂���u���Ă���ƁA�O�����炻�̌����͊Ǘ�����Ă��Ȃ��ƔF������A�₪�đ��̑������ׂĔj��A������r���S�̂��r�p���邱�ƂŁA����ɂ��̒n�悪�r��Ă��܂��v�Ƃ����l�����ŁA�����Ȕƍ߂̉�����������Ώ����Ă������ƂŁA�n��S�̂����S���ĕ�点��n���ۂƂ������̂ł��B
 ����ł́A��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂����A�F�h�Ɠ��̌��ʂɂ��Ăǂ̂悤�ɔF�����Ă��܂����B
����ł́A��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂����A�F�h�Ɠ��̌��ʂɂ��Ăǂ̂悤�ɔF�����Ă��܂����B
 �F�h�Ɠ��ɂ��ẮA�e���r�Ō��ʂ�����ƕ��ꂽ���Ƃɂ��A�F�h�Ɠ����ݒu����Ă���ꏊ�͖h�ƈӎ��������n�悾�Ɣƍߎ҂��F�����邱�Ƃň��̗}�~���ʂ͂���Ǝv���܂��B�������F�h�Ɠ����̂ɔƍߗ}�~�̌��ʂ�����Ƃ����Ȋw�I�Ȏ��،��ʂ͔�������ĂȂ��ƔF�����Ă��܂��B
�F�h�Ɠ��ɂ��ẮA�e���r�Ō��ʂ�����ƕ��ꂽ���Ƃɂ��A�F�h�Ɠ����ݒu����Ă���ꏊ�͖h�ƈӎ��������n�悾�Ɣƍߎ҂��F�����邱�Ƃň��̗}�~���ʂ͂���Ǝv���܂��B�������F�h�Ɠ����̂ɔƍߗ}�~�̌��ʂ�����Ƃ����Ȋw�I�Ȏ��،��ʂ͔�������ĂȂ��ƔF�����Ă��܂��B
 ��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂��B���ݕ��ƊX�H���̈ӐFLED���ɂ��h�Ƒ�ɂċ��c���s�������Ƃ͂���܂����B
��@�Ǘ��S�������Ɏf���܂��B���ݕ��ƊX�H���̈ӐFLED���ɂ��h�Ƒ�ɂċ��c���s�������Ƃ͂���܂����B
 �K�v�ɉ����ď��̋��L�͍s���Ă���܂����A��̓I�ȋ��c�ɂ��Ă͍s���Ă͂���܂���B
�K�v�ɉ����ď��̋��L�͍s���Ă���܂����A��̓I�ȋ��c�ɂ��Ă͍s���Ă͂���܂���B
 ����ł́A���㋦�c���Ă������l���͂���܂����B
����ł́A���㋦�c���Ă������l���͂���܂����B
 �K�v�ɉ����ċ��c���Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
�K�v�ɉ����ċ��c���Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
 ���ݕ����Ɏf���܂��B����X�H���X�V��V�݁A���邢�͓d���̌����ɓ������ẮA�FLED�d���֍D�����Ă������Ƃɂ��āA�������Ă��������邩�A���l���������������������B
���ݕ����Ɏf���܂��B����X�H���X�V��V�݁A���邢�͓d���̌����ɓ������ẮA�FLED�d���֍D�����Ă������Ƃɂ��āA�������Ă��������邩�A���l���������������������B
 .��قǓ��ق��܂������A���FLED���ɂ��܂��ẮA�����Q�R�N�P�Q���P���łP�R�O���ݒu���Ă���Ƃ���ł������܂��B���������ݒu��i�߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B
.��قǓ��ق��܂������A���FLED���ɂ��܂��ẮA�����Q�R�N�P�Q���P���łP�R�O���ݒu���Ă���Ƃ���ł������܂��B���������ݒu��i�߂Ă��������ƍl���Ă���܂��B
�Ȃ��A�FLED���ɂ��܂��ẮA���s�̓��H�Ɩ����ɗp�����Ă��锒�F�̌��ɔ�ׂ܂��āA�g���̒Z���F�̌��́A�J�▶�̒��ł͋ɓx�Ɏ��F�����ቺ����Ƃ������Ă��܂����A�l�X�Ȉӌ�������悤�ł��̂ŁA�Ȋw�I�Ȏ��،��ʂ̔����ȂǁA������x�̌��ʂ��m�F�ł�����̐ݒu�������������ƍl���Ă���܂��B
 ��@�Ǘ��ƌ��ݕ��Ƃ��ɘA�g���Ă��������āA�ߓd�Ɩh�Ƃ̈�Γ�_���Ă������������Ǝv���Ă��B
��@�Ǘ��ƌ��ݕ��Ƃ��ɘA�g���Ă��������āA�ߓd�Ɩh�Ƃ̈�Γ�_���Ă������������Ǝv���Ă��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 ����w�O���ւ̃z�e���U�v�ɂ���
����w�O���ւ̃z�e���U�v�ɂ���
����w�O���ւ̃z�e���̗U�v�ɂ��Ďf���܂��B���̎���͍�N�x�Q��s���܂������A����łR��ڂɂȂ�܂��B
�{����ɁA��T������s�����v��̑����I�Ɏ��g�ޏd�_�ۑ�̈�ł���A�u����u�����h�̑n���ƒn��o�ς̊������v�𐄐i���邽�߂̑g�D�@�\�̉����c�Ă���Ă���Ă��܂��B
���̏d�_�ۑ�͊�{�v��ɂ��ƁA�u�{�s�����������̎�����L�@�I�ɋ@�\�����A���������̏���u�����h����i�߁A�܂��V���ɖ��͂@���A�n��o�ς̊����������g�݂܂��B�v�Ƃ���Ă��܂��B�����ŁA�������������Ɋm�F�����Ă��������܂�
 �u�V���Ȗ��͂@���v�Ƃ���܂����A���̈Ӗ�����Ƃ���́u���łɏ���ɑ��݂��Ă��邪�A�F�m����Ă��Ȃ����͓I�Ȃ��̂��݂������v�Ƃ������ł��傤���B
�u�V���Ȗ��͂@���v�Ƃ���܂����A���̈Ӗ�����Ƃ���́u���łɏ���ɑ��݂��Ă��邪�A�F�m����Ă��Ȃ����͓I�Ȃ��̂��݂������v�Ƃ������ł��傤���B
 ��T������s�����v��ł́u����u�����h�̑n���ƒn��o�ς̊������v�𐄐i���邽�߂Ɂu�V���Ȗ��͂̔��@�v�������Ă���܂����A���̈�Ƃ��Ė{�s�����ݓI�Ɏ����Ă���܂����͓I�Ȏ����@���L���F�m���Ă��������ƌ��������������܂��B
��T������s�����v��ł́u����u�����h�̑n���ƒn��o�ς̊������v�𐄐i���邽�߂Ɂu�V���Ȗ��͂̔��@�v�������Ă���܂����A���̈�Ƃ��Ė{�s�����ݓI�Ɏ����Ă���܂����͓I�Ȏ����@���L���F�m���Ă��������ƌ��������������܂��B
�܂��{�s�ɂ́A�D�ꂽ�H�Ɛ��i��_�Y���A���邢�͖L���Ȏ��R����j�A������v���X�|�[�c���́u�ʃu�����h�v���������܂����������������́u����u�����h�v�ƐV���ɔ��@���ꂽ������L�@�I�ɘA�g����邱�Ƃɂ��܂��āA������ʂƂ��Ắu�V���Ȗ��͂̔��@�v�ɂȂ��邱�Ƃ��ł��A�u�s�s�C���[�W�Ƃ��Ă̏���u�����h�v�������グ�Ă܂��肽���Ǝv���Ă���܂��B
 ���������������������ɂ��q�˂������܂�
���������������������ɂ��q�˂������܂�
����w�O���Ƀz�e�����ł����ꍇ�A���̃z�e���́u����u�����h�̑n���v�ɂǂ̂悤�Ȍ��ʂ�����ƍl���܂���
 �u����u�����h�v�ɂ́u�ʃu�����h�v�u�s�s�C���[�W�Ƃ��Ẵu�����h�v��������̂ƂƂ炦�Ă���܂��B
�u����u�����h�v�ɂ́u�ʃu�����h�v�u�s�s�C���[�W�Ƃ��Ẵu�����h�v��������̂ƂƂ炦�Ă���܂��B
�c������̃z�e��������w���ӂɂł����ꍇ�ɂ́A���ꂪ�����h�}�[�N�I�Ȃ��̂ɂ��Ȃ肦�܂��̂ŁA�z�e�����̂��̂��u�ʃu�����h�v�ɂȂ�\�����\�������Ă�����̂Ǝv���Ă���܂��B
�܂��A�z�e���ɂ���Ă̓R���x���V�����@�\�Ȃǂ̕����I�ȕt�ѐݔ�������Ă�����̂��������܂��̂ŁA�����������̂����ӂ̓s�s�@�\��i�ρA����ɂ͑��̌ʃu�����h�ƗL�@�I�ȘA�g��}�邱�ƂŁA�u�s�s�C���[�W�Ƃ��Ă̏���u�����h�v����w���߂邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���܂��B
 ���Ɏs���o�ϕ����ɂ��������܂��B
���Ɏs���o�ϕ����ɂ��������܂��B
����w�O���Ƀz�e�����ł����ꍇ�A�u�n��o�ς̊������v���}����ƍl���܂����B
 �w�O���Ƀz�e�������݂��ꂽ�ꍇ�ɂ́A����܂łɂȂ����͂������ɉ����A�s�X����̂��q�l�A������𗬐l���̑����ɂ��o�ϊ����������҂ł�����̂ƍl���Ă���܂��B
�w�O���Ƀz�e�������݂��ꂽ�ꍇ�ɂ́A����܂łɂȂ����͂������ɉ����A�s�X����̂��q�l�A������𗬐l���̑����ɂ��o�ϊ����������҂ł�����̂ƍl���Ă���܂��B
 ���ɂ܂��Â���v�敔���ɂ��q�˂������܂��B
���ɂ܂��Â���v�敔���ɂ��q�˂������܂��B
����w���ӂ̂܂��Â���ɂ��Ắu����w���ӂ܂��Â����{�\�z�v�������Q�P�N�U���ɍ��肳��Ă������Ǝv���܂��B�܂��A��T������s�����v����X�^�[�g���܂������A���������\�z����v��ɁA����̐����A���ɐ����S���ԗ��H��Ւn���ӂ̂܂��Â���ɂ��ẮA�ǂ̂悤�Ɉʒu�Â����Ă���̂��B���݂̐i���y�э���̗\����܂߂��������������B
 �u����w���ӂ܂��Â����{�\�z�v�Ȃǂ܂�����T�������v��ɂ����܂��Ă͏���w�����n��̌v��I�ȓy�n���p��}�邽�ߓ��H�E�������̊�Ր�����Z���̐����E���P�����s���A�{�s�̕\���ւɂӂ��킵���X�Â���������߂�Ƃ���Ă���܂��āA�u����S�N�Ԃɏd�_�I�Ɏ��g�ގ��Ɓv�Ɉʒu�t���Ă���܂��B
�u����w���ӂ܂��Â����{�\�z�v�Ȃǂ܂�����T�������v��ɂ����܂��Ă͏���w�����n��̌v��I�ȓy�n���p��}�邽�ߓ��H�E�������̊�Ր�����Z���̐����E���P�����s���A�{�s�̕\���ւɂӂ��킵���X�Â���������߂�Ƃ���Ă���܂��āA�u����S�N�Ԃɏd�_�I�Ɏ��g�ގ��Ɓv�Ɉʒu�t���Ă���܂��B
���݂̐i���y�э���̗\��́A�u���Ԋ��͂̓����v�̎��_�Ȃǂ���A�s�AUR�s�s�@�\�y�ѐ����S��������Ђ̂R�҂Ŏ��Ǝ�@�Ȃǂ̋��������������Ƃɗ��N�x�͊w���L�����ҁA�n����\�҂Ȃǂ������������ψ���Ȃǂ�݂��A�n���̊F�l���n�ߊW�҂̂��ӌ������܂��Ȃ���A���{�Ɍ���������̂̌v��Â����i�߂Ă܂��肽���ƍl���Ă���܂��B
 ���Ɖ��܂ł́A�������Ԃ������肻���ł����A�\�z�������̓I�Ȏ�n������܂��B���Ƃ͐i�o���Ă����z�e���܂��Ƃ����邩�ǂ����A�Ƃ��������Ǝv���܂����A��̓I�ȗU�v���������Ă����Ȃ���Ύ���������̂ł͂���܂���B
���Ɖ��܂ł́A�������Ԃ������肻���ł����A�\�z�������̓I�Ȏ�n������܂��B���Ƃ͐i�o���Ă����z�e���܂��Ƃ����邩�ǂ����A�Ƃ��������Ǝv���܂����A��̓I�ȗU�v���������Ă����Ȃ���Ύ���������̂ł͂���܂���B
 �Ō�Ɏs���Ɏf���܂��B
�Ō�Ɏs���Ɏf���܂��B
�s���́A�u�����E�u�����h�v�u�����̕��@�O��}�`�@����v�Ƃ��āA����u�����h�̎x���⏤�H�Ƃ̔��W�̌㉟��������Ƒz��������Ă���܂��B���������Ȃ��A�n��o�ς̊�������Ƃ��ẮA�b��s�X���������⏊��C���^�[�`�F���W���ӂȂǁA�s���ւ̊�ƗU�v������������Ă��邩�Ǝv���܂��B�܂��A����s�̃l�[���o�����[������ɍ��߂邽�߂ɂ��A�z�e���̗U�v�͕K�v���Ǝv���܂��B�z�e���̗U�v�ɂ������Ă͒n���҂��l����ΐ����n���]�܂����̂ł����A�Ȃ��Ȃ�����ʂ�����悤�ł��B�Ⴆ�ΌŒ莑�Y�ł̌��ƍ�����ł��o���Ȃǂ��āA�ϋɓI�Ɋ�Ƃɓ��������Ă������������Ǝv���܂����A�s���Ƃ��Ă̂������������������������B
 ��������Ƃ��Ă����������Ă����������u�������v�ɂ́u�s�s���Ȃǂ��������A�l���Ƃ��Ăэ��ށv���߂̕���Ƃ��āA�b�蒲�����⏊��C���^�[�`�F���W���ӂȂǂ̓s�s�v����������A��ƗU�v��i�ߍΓ��A�b�v�ɓw�߂邱�Ƃ��f���Ă���܂��B
��������Ƃ��Ă����������Ă����������u�������v�ɂ́u�s�s���Ȃǂ��������A�l���Ƃ��Ăэ��ށv���߂̕���Ƃ��āA�b�蒲�����⏊��C���^�[�`�F���W���ӂȂǂ̓s�s�v����������A��ƗU�v��i�ߍΓ��A�b�v�ɓw�߂邱�Ƃ��f���Ă���܂��B
�c������Ẵz�e���ɂ��܂��Ă��A��Ƃ��L���Ӗ��łƂ炦���ꍇ�A�Ώۂ̈�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�������Ȃ���A�z�e���𗘗p�������Ƃ������v�������Ă̗U�v�Ƃ������ɂ��Ȃ�܂��̂ŁA�܂��͖{�s�̂����͓I�Ȏ��������u����u�����h�v�����߁A�����̏����s���O�Ɍ��ʓI�ɔ��M���A��葽���̕��X�ɏ����m���Ă��������A�S�������Ă������������ƍl���Ă���܂��B
�܂��A�Œ莑�Y���ƂȂǂ̗D����ɂ��ẮA��ƗU�v�̍ۂ̃C���Z���e�B�u�v�f�Ƃ��ėL���Ȏ�i�Ƃ��čl�����܂��̂ŁA���s�̏����m�F���Ȃ��獡�㌤����v����ۑ�Ƃ��ĂƂ炦�Ă���܂��B
������ɂ������܂��Ă��A��ƗU�v��i�߂邽�߂ɂ́A�s�Ƃ��Ă̂�������Ƃ������j�����肵�������ŁA�ϋɓI�Ɋ�ƂɃA�v���[�`���Ă��������ƍl���Ă���܂��B
 ���Ȃ݂ɋc��Ƃ��āA���s�c���̎��@�̎�����тł����A�����Q�Q�N�x�́A�W�Q�c�̂U�W�T���ł��B���̒��Ŏs���ɏh�����������͂P�P���W�X���ł����B
���Ȃ݂ɋc��Ƃ��āA���s�c���̎��@�̎�����тł����A�����Q�Q�N�x�́A�W�Q�c�̂U�W�T���ł��B���̒��Ŏs���ɏh�����������͂P�P���W�X���ł����B
�V���Ƀz�e�����ł����ꍇ�ł��A���@����������܂�����S�ď���s�ɏh������킯�ł͂���܂��A���̐��͑�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
�����āA�����K�ꂽ�e�s�̋c�����n���ɋA���āA����s�̐�i�I�Ȏ{���łȂ��A����u�����h���Љ�Ă����A���@�҂͂������ł����A����ȊO�̕��X������s�ɖڂ������Ă������̂Ǝv���Ă��܂��B
���̎���͍���������Ă܂���܂��̂ŁA�\�������̂قǂ�낵�����肢�������܂��B
 �ڎ��ɖ߂�
�ڎ��ɖ߂�
 �`���{��̋������n�邱�Ƃɂ��ā`
�`���{��̋������n�邱�Ƃɂ��ā` �`�w�щ��P�v���W�F�N�g�ɂ��ā`
�`�w�щ��P�v���W�F�N�g�ɂ��ā` �w�K�x�����ɂ���
�w�K�x�����ɂ��� ����n��̈�ِ����ɂ���
����n��̈�ِ����ɂ��� �X�H����LED���E�h�Ƒ�ɂ���
�X�H����LED���E�h�Ƒ�ɂ��� ��@�Ǘ��ƌ��ݕ��Ƃ��ɘA�g���Ă��������āA�ߓd�Ɩh�Ƃ̈�Γ�_���Ă������������Ǝv���Ă��B
��@�Ǘ��ƌ��ݕ��Ƃ��ɘA�g���Ă��������āA�ߓd�Ɩh�Ƃ̈�Γ�_���Ă������������Ǝv���Ă��B